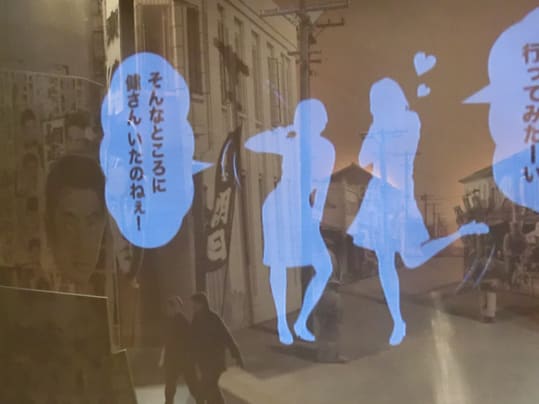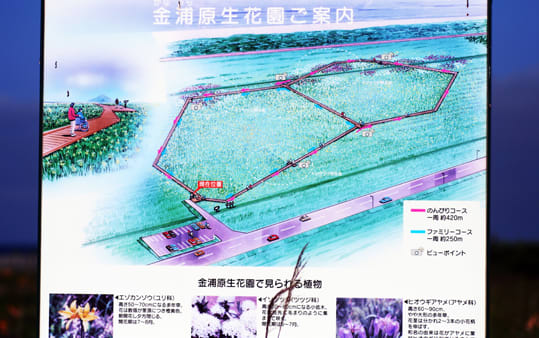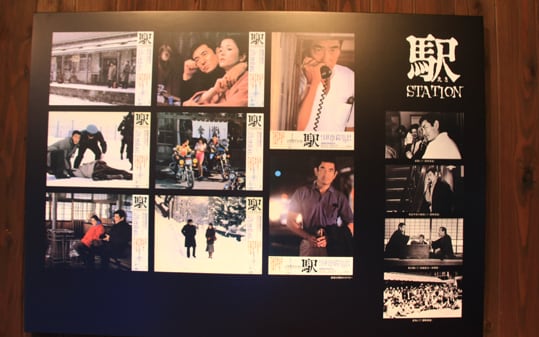函館駅近くの国際ホテルを朝5時に出たときにに小雨がぱらついていました。雨が降ってはせっかくの松前桜が…と心配しましたが、やがて降ったり止んだり、一時日も差す状況に変わってきました。今日のスケジュールは、渡島当別のトラピスト、松前公園の桜、江差港の開陽丸、夕陽が出れば岩内港で夕陽の撮影と考えておりました。午前6時過ぎにトラピストに到着してみると、桜は全く咲いておりません。固いつぼみのままです。緯度的には函館とほぼ同じでありながら、一方は満開、他方は固いつぼみのままという、ちぐはぐに驚きです。
(1) 渡島当別のトラピスト
ご存じのように、湯の川にあるのが女子修道院のトラピスチヌで、こちらは男子修道院のトラピストです。湯の川の方は敷地の一部が観光用に開放されて、売店などもありますが、トラピストの方は観光客は一切立ち入り禁止です。
![]()
(トラピストに続く道は杉木立があってとても綺麗)
![]()
(高い塀に沿って裏側に出ると、山にもやがかかって幻想的)
(2) 福島町の水産加工場
福島町は横綱の里として有名です。昭和20年代には「突っ張り」の名横綱千代の山が、また50年代には横綱千代の富士が誕生している。両横綱を記念した横綱記念館もありますが、時間が早く開館しておりませんでした。ふと道路一本向うの水産加工場を見ると、女工さんたちが何やら話し声が聞こえます。すかさず、写真撮影です。ずうずうしく工場内に入り込み撮らせていただきました。
![]()
(冷凍でガチンガチンのイカを真水でほごしているようです)
![]()
(だいぶほごれてきました スルメに加工する一工程だとか…)
![]()
(ほごしが終わって次の工程に… シャッターを閉めるということで我々は外に出ました)
(3) 松前公園の桜
日本最北の白、松前城を中心にこの公園には光善寺などのお寺や松前神社が付随してあり、さらに観光施設として「松前藩屋敷」(案内板左上)が再現されています。観光案内によれば、250種1万本の桜があるそうです。5月7日に訪れた際には、染井吉野はややピークを過ぎておりましたが、濃いピンク色で八重の「南殿(ナデン)」は満開でした。
![]()
(公園入り口の案内板)
![]()
(お城と桜の定番写真ですが…)
![]()
(堀に映る白と桜をPEN E-P1で幻想的に撮ってみました)
![]()
(松前桜三大銘木の一つ「夫婦桜」 染井吉野と南殿が寄り添うように生えていることから「夫婦」の名前が付けられた)
![]()
(椿の落花と桜の花が同時に落ちているのも北海道ならではのこと)
![]()
(光善寺の「血脈桜」 松前桜三大銘木の一つ)
なお、血脈桜という聞きなれない言葉に戸惑う方が多い事でしょう。血脈とはお坊さんが浄土に旅立つ人に仏になるために与える証のことを言います。光善寺のの桜は、あるとき本堂改修のために伐採されることになりました。ところが伐採前日に、住職の枕元に、桜の精が現れ、血脈を欲しがったそうです。やむなく血脈を与えると、伐採当日その血脈が桜の木から落ちてきました。これに驚いた住職が、桜の精を憐れんで供養するとともに、伐採を取りやめました。という言い伝えから「血脈桜」と呼んでいます。
さてせっかくですから「松前藩屋敷」を訪ねてみましょう。350円の通行手形を買って中に入ると、関所があって、呼び止められました。
![]()
(はは〜、お代官様、あっしはなにも悪いことは…身に覚えがありません 平謝りの図)
![]()
(商家を覗いてみると…)
![]()
(時代衣装を身に着けた飴売りの娘さん モデルになっていただきました、50円の水あめを買って…)
松前での桜撮影を終わって、江差に向かいます。江差で昼食後、海岸に係留されている幕末時代に活躍した「開陽丸」を撮影しました。取り上げる程の画像でもありません。そのまま海岸線を北上します。
(4) 弁慶岬
北海道内には、結構源義経主従に関する伝説があちこちにあります。平泉で頼朝の軍に敗れた義経主従は敗走し、津軽海峡を渡り、北上して蝦夷地から日本海を渡ってモンゴルに逃れた。そしてチンギスハーンになった、という突飛な伝説があるんです。この弁慶岬もその伝説の一つで、ここに逗留した弁慶が、舎弟の常陸坊海尊が義経再挙の兵を募り蝦夷地に向かったという話を聞き、毎日この岬で待っていたという言い伝えです。
![]()
(公園の東屋から弁慶の像を見る)
なお、ここ寿都町の弁慶岬を国道229号線に沿って40?ほど岩内町方面に進むと、雷電岬があ理ます。その突端に切り立つ崖を「弁慶の刀掛け」の岩と呼んでいます。ここを通った弁慶一行が一休みしたときに、岩を一ひねりして腰の刀をかける岩を作ったという伝説です。現在は付近を通る国道がトンネル化されたために、見にくくなってしまいました。
(5) 岩内漁港の落日
どうやら落日寸前に岩内漁港に到着しました。漁船かカモメをバックに消波堤ブロックの向うに沈む夕日を撮ろうというつもりです。あと数分で太陽が落ちてしまいます。漁港を駆け回り撮影スポットを探します。運よく漁船と水たまり、カモメが見えました。
![]()
(よく見るとカモメが二羽います。逃げない程度に近づきます)
![]()
(タイミングよく羽を広げました)
撮影を終わった時はすでに日は落ちて、暗闇が迫ってきました。あとは小樽に戻るだけです。
(1) 渡島当別のトラピスト
ご存じのように、湯の川にあるのが女子修道院のトラピスチヌで、こちらは男子修道院のトラピストです。湯の川の方は敷地の一部が観光用に開放されて、売店などもありますが、トラピストの方は観光客は一切立ち入り禁止です。

(トラピストに続く道は杉木立があってとても綺麗)

(高い塀に沿って裏側に出ると、山にもやがかかって幻想的)
(2) 福島町の水産加工場
福島町は横綱の里として有名です。昭和20年代には「突っ張り」の名横綱千代の山が、また50年代には横綱千代の富士が誕生している。両横綱を記念した横綱記念館もありますが、時間が早く開館しておりませんでした。ふと道路一本向うの水産加工場を見ると、女工さんたちが何やら話し声が聞こえます。すかさず、写真撮影です。ずうずうしく工場内に入り込み撮らせていただきました。

(冷凍でガチンガチンのイカを真水でほごしているようです)

(だいぶほごれてきました スルメに加工する一工程だとか…)

(ほごしが終わって次の工程に… シャッターを閉めるということで我々は外に出ました)
(3) 松前公園の桜
日本最北の白、松前城を中心にこの公園には光善寺などのお寺や松前神社が付随してあり、さらに観光施設として「松前藩屋敷」(案内板左上)が再現されています。観光案内によれば、250種1万本の桜があるそうです。5月7日に訪れた際には、染井吉野はややピークを過ぎておりましたが、濃いピンク色で八重の「南殿(ナデン)」は満開でした。

(公園入り口の案内板)

(お城と桜の定番写真ですが…)

(堀に映る白と桜をPEN E-P1で幻想的に撮ってみました)

(松前桜三大銘木の一つ「夫婦桜」 染井吉野と南殿が寄り添うように生えていることから「夫婦」の名前が付けられた)

(椿の落花と桜の花が同時に落ちているのも北海道ならではのこと)

(光善寺の「血脈桜」 松前桜三大銘木の一つ)
なお、血脈桜という聞きなれない言葉に戸惑う方が多い事でしょう。血脈とはお坊さんが浄土に旅立つ人に仏になるために与える証のことを言います。光善寺のの桜は、あるとき本堂改修のために伐採されることになりました。ところが伐採前日に、住職の枕元に、桜の精が現れ、血脈を欲しがったそうです。やむなく血脈を与えると、伐採当日その血脈が桜の木から落ちてきました。これに驚いた住職が、桜の精を憐れんで供養するとともに、伐採を取りやめました。という言い伝えから「血脈桜」と呼んでいます。
さてせっかくですから「松前藩屋敷」を訪ねてみましょう。350円の通行手形を買って中に入ると、関所があって、呼び止められました。

(はは〜、お代官様、あっしはなにも悪いことは…身に覚えがありません 平謝りの図)

(商家を覗いてみると…)

(時代衣装を身に着けた飴売りの娘さん モデルになっていただきました、50円の水あめを買って…)
松前での桜撮影を終わって、江差に向かいます。江差で昼食後、海岸に係留されている幕末時代に活躍した「開陽丸」を撮影しました。取り上げる程の画像でもありません。そのまま海岸線を北上します。
(4) 弁慶岬
北海道内には、結構源義経主従に関する伝説があちこちにあります。平泉で頼朝の軍に敗れた義経主従は敗走し、津軽海峡を渡り、北上して蝦夷地から日本海を渡ってモンゴルに逃れた。そしてチンギスハーンになった、という突飛な伝説があるんです。この弁慶岬もその伝説の一つで、ここに逗留した弁慶が、舎弟の常陸坊海尊が義経再挙の兵を募り蝦夷地に向かったという話を聞き、毎日この岬で待っていたという言い伝えです。

(公園の東屋から弁慶の像を見る)
なお、ここ寿都町の弁慶岬を国道229号線に沿って40?ほど岩内町方面に進むと、雷電岬があ理ます。その突端に切り立つ崖を「弁慶の刀掛け」の岩と呼んでいます。ここを通った弁慶一行が一休みしたときに、岩を一ひねりして腰の刀をかける岩を作ったという伝説です。現在は付近を通る国道がトンネル化されたために、見にくくなってしまいました。
(5) 岩内漁港の落日
どうやら落日寸前に岩内漁港に到着しました。漁船かカモメをバックに消波堤ブロックの向うに沈む夕日を撮ろうというつもりです。あと数分で太陽が落ちてしまいます。漁港を駆け回り撮影スポットを探します。運よく漁船と水たまり、カモメが見えました。

(よく見るとカモメが二羽います。逃げない程度に近づきます)

(タイミングよく羽を広げました)
撮影を終わった時はすでに日は落ちて、暗闇が迫ってきました。あとは小樽に戻るだけです。